
こんちは、モチです!
今回は『相談ができない』という方に向けた対策を紹介していきます。

相談することが苦手なので、是非参考にさせて頂きます!
職場において『困ったことがあれば気軽に相談して』はよく聞くフレーズですが、皆さんは相談する際に躊躇することはありませんか?
筆者は新入社員時代、上司に不明なことを星の数ほど相談した経験がありますが、上司の回答は『それくらい自分で考えろ』、『それって相談すること?』など、かなり塩対応を受けたものです。
そして、だんだんと相談がしずらくなり、自分で仕事を判断した結果、、、
『どうして相談しなかったの?』
このセリフを聞いた時に、何が相談すべきことでしないことなのか混乱してしまい、相談することに少しばかりの怖れを感じていました。

その気持ちすごくよくわかります。私も何が相談の基準かわからないです。

しかし、トライ&エラーを繰り返した結果、『相談する基準』に気づくことができました!
長年業務経験をして罵られた結果わかったことは、相談に至るには『ある基準』を満たす必要があります。そのルールをしっかり守れば、今まで苦痛と感じていた相談業務が想像以上に簡単にできるようになります。
当記事では、職場で欠かせない相談業務を行うための『3つの判断基準』と『相談を上手くする準備』の2つについて詳しく解説してまいります。
『相談が苦手』、『相談するのが怖い』と感じている人は、本記事を読んですぐ実践してみて下さい。今まで悩んでいたものが明確になり、業務効率向上も期待できるので必見です!
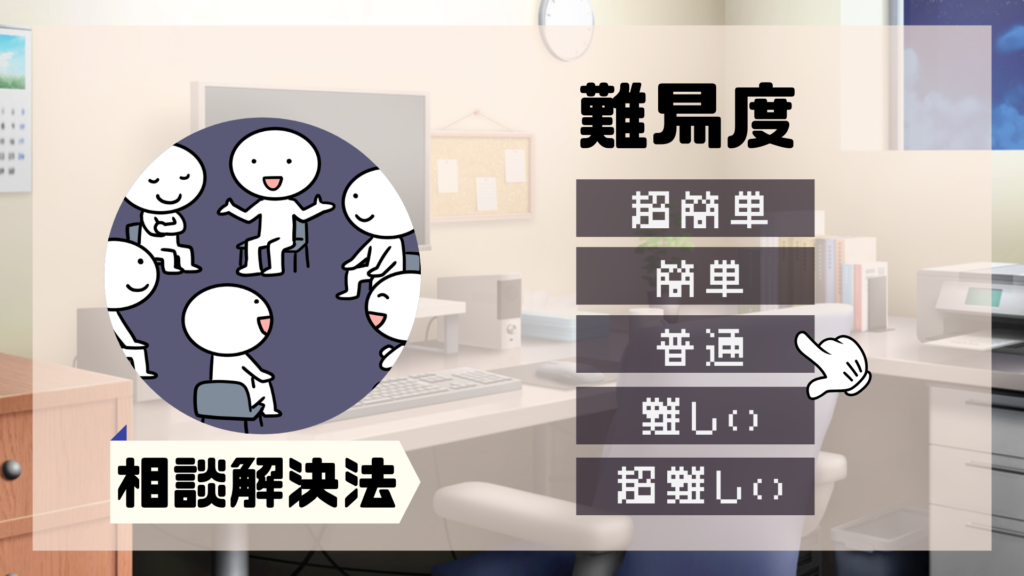
当記事は、大きく2つのパートに分けて相談の手順を解説してまいります。

アンダーバーをクリックすると、飛ばし読みをすることができます!
相談の判断基準

近年の若者は、相談をしない人が多いとよく耳にします。現代はインターネットの情報がありふれていて、不安があればネットで検索解決という人も少なくないようです。

私も相談するのに躊躇してしまい、ググって仕事を進行しがちですね。

気持ちはわかります。
ですが、必要最低限の相談はすべきだと私は思います。
会社というものは組織で成り立っており、相談を怠れば組織は機能せず、最悪会社経営の危機に陥ることもあるでしょう。それくらい相談は大切なものだということをはじめに理解して頂きたいです。
既に相談の重要性を理解している方もいるかと思いますが、今読者様はこう感じているはずです。
『じゃあ、どうすれば相談が上手くできるようになるんだよ!?』
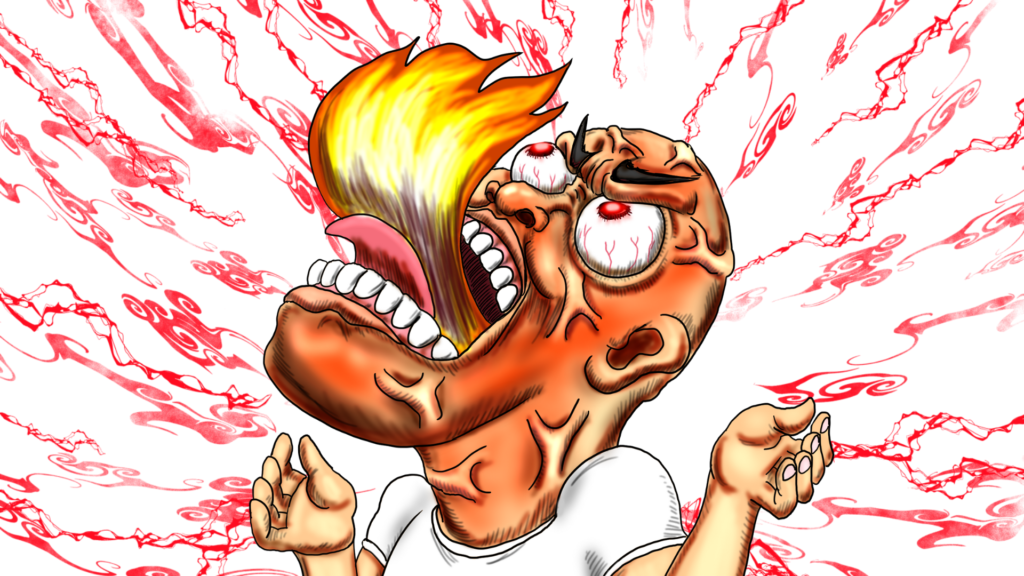
まったくその通りです。勇気を出して相談しても、上司から冷たくあしらわれたら2度と相談なんてしたくないと思ってしまいますよね。

ですが、相談する際、少し考えて頂きたいことがあります。
あなたは誰かに相談するとき、『自分主体で相談している』なんてことありませんか?
もちろん相談するということは、あなたが不明・不安な点を同僚や上司に打ち明けることですが、『あなたにしかわからない』ことや『調べればわかること』も存在しています。

あなたにしかわからないことを相談されても、人は的確なアドバイスをあなたに伝えられません。むしろ、それを相談してもお互い時間の無駄になってしまいます。
相談が苦手な人ほど、相談する『判断基準』を理解できていないと私は感じています。
筆者の経験と今まで指導してきた後輩の実例を含めて、『相談すべきこと』と『相談すべきでないこと』の基準を、次のパートで詳細に解説をしてまいります。
3つの判断基準

まず、相談をする前に考えなければいけない項目が3つあります。これらの項目をすっとばして自分の思いついたまま相談すると、残念ながら冷たくはねのけられてしまう可能性があります。

相談をする際に考えるべきことは、あなたが情報をもっているかいないかで判断します。

具体的にどのような情報なのでしょうか?
あなたが持てる情報を自覚している方は、情報の整理がされている状態なので、受け手側はあなたが何についてわからないかということがすぐに理解できます。
では、あなたが所有してる情報とは一体何なのなのでしょう?

考えられるものは、大きく3つあります。
- ググってわかる情報
- 自分が管理している情報
- 既に教えてもらった情報
上記3つの情報があなたが保有しているもので、この3つ以外の情報について相談するのが正解だと私は思っております。

判断基準である情報の具体例も参考にしてみて下さい。
ググってわかる情報
ググるという言葉をご存じの方は多いと思いますが、簡潔にまとめると、ネットで調べられる知識程度の情報は相談する必要がないということです。
例えば、専門用語や業界常識の単語の意味、某有名なコンピューターソフトの使い方、価格相場など、上司に聞かなくても調べられる情報は多々あります。
企業でしか使っていないソフトウェアなども、マニュアルを読めば相談する必要がありません。

上司の『自分で考えろ』、『それ相談すること?』という対応は、自分で本当に調べたうえで質問しているのかということを意味しています。
筆者が新人時代に上司に相談してもあしらわれたのは、本当に調べつくすまで調べていなかったことが原因だと考えています。
学生時代は先生や教授に指示されたことをやっていればよかったですが、社会人は自分で調べる力が必要になってきます。
『これはどういう意味や意図があるのか?』、『なぜこうなったのか?』など、自分で考えることはとても大切です。もし自分で考えられないのであれば、会社はあなたを必要とせず、今後は機械があなたの仕事をやることになるでしょう。

しかし、ググってもわからない情報もあると思います。

そうですね、そこではじめて相談する条件を満たしているのだと思います。ただ、調べつくしたという行動がとても大切なのです。
もし後輩や部下に、『〇〇についてここまで調べてみたのですが、自分の知識では不十分のために△△について質問させて頂きたいです。』と聞かれたらあなたはどう感じますか?

相談者の努力や力量を把握することができますね。
たいして調べもせずに、〇〇がわかりませんと言われても、相談者がどれくらい仕事を理解しているかが把握しずらく、教え方も色々考えなければいけません。
ここまではOKで、ここからがわからないという、『具体的な不明点』を上司や同僚は知りたいのが本音です。

極端な例でいえば、リンゴについて教えて下さいと聞かれたら、私は何を伝えればいいのかわかりません。
質問者が求めているのは、りんごの外見がわからないのか、味がわからないのか、どこが生産地なのかなど、相手が何を知りたいかを受け手側は考えなければいけません。
あなたが誰かに仕事の相談をするときは、『どこまで調べて』、『どんなことがわからないのか』をまずは明確にしてから質問をして下さい。
自分が管理している情報
業務情報の中には、あなたしか管理していない情報というものがあります。
あなた以外に誰もその情報を詳しく知らないのに、上司に相談しても的確なアドバイスをもらえることはおそらくできません。むしろ、あなたは忙しい上司の邪魔をしている可能性があります。

私しか知らない情報なんてあるんですか?

例えば萌智さんのデスク周辺は、萌智さん以外ほとんどの人は知らないはずですよ。
あなたしか知らない情報を例にすると、あなたのデスクがイメージしやすいかと思います。顧客データ、資料、保存ファイルなどは、あなた以外誰も詳しくわかりません。
重要な資料データをどこかのファイルに入れて見つからない、ある顧客の対応をどのようにすればいいかなどの情報は、上司は全くわかりません。
ある程度のアドバイスはできたとしても、どんな経緯かわからないものについて相談されても、的確な指示を与えることは残念ながら不可能です。

自分が相手の立場に立ってみて、質問されて答えられるかを考えてみましょう。
上司は何でも知っているスーパーマンではありません。あなたしかわからない情報はあなたしか答えが出せないのです。
但し、自分で問題を抱え込みすぎる方もいるので、自分なりに考えたことを上司に相談してみるのはアリだと私は思っています。上司もあなたのような経験をした可能性もあるので、まずは情報整理を優先して、わからないところは相談というスタイルでいきましょう。
既に教えてもらった情報
教えてもらった情報については、再度聞き直すことに抵抗があると思います。
教えてもらったことを忘れたという自覚があればまだいいですが、私みたいな記憶力がない方は、指導されたことすら覚えていないからたちが悪いです。

しかし、覚えてないものは仕方ないと割り切って、質問して全然問題なしです!
世間では1聞いて10を学べと言われますが、それは優秀な人ができる特殊能力であって、普通の会社員は1聞いて1か2覚えるのがいいくらいです。
教えてもらうときに、メモを取ることもあるかと思いますが、メモを読み返してもイマイチわからないこともあります。
そんな時は、『申し訳ございません、1度伺ったことですが〇〇について再度教えて下さい!』とハキハキと気持ちよく質問していきましょう。

大切なのは、次も同じ過ちを起こさないことです。
業務では、メモ取り1つでも簡単ではありません。どうやったら上手くメモを取れるかは、別記事の仕事の覚えの悪さを解決するたった3つの手順を紹介で解説しているので、是非参考にしてみて下さい。

上記方法でも上手くいかない方は、ボイスレコーダーや動画などを撮って、復習をすると良いです。
メモを取ることがどうしてもできない人は、会社の承諾をもらって動画やボイスレコーダーを取ることをおすすめします。但し、携帯のボイスレコアプリは近距離でないと音をきれいに拾うことができないので、業務用のボイスレコーダーを使うことをおすすめします。

ちなみに、私が愛用しているボイスレコーダーは下記です。
オリンパス OLYMPUS ステレオICレコーダー Voice Trek V-873 ブラック 8GBは、とてもシンプルな操作性と、遠くの小さな音も録音できるのが大きな特徴です。
筆者もオンラインインタビューで利用していますが、モニター越しでもかなり小さな音を拾ってくれるので愛用しています。また、バッテリーもUSB充電なので非常に便利です。
宣伝はここまでにして、ボイスレコーダーや動画は、言った言わないの証拠も残り、聞き直す手間を省くことができるので、とてもおすすめな方法だと思います。

なるほど~
上記3つの判断基準以外のものについて相談するとルールを作ってしまえばいいんですね。
相談の準備

相談の判断基準が理解できれば、あとは相談するのみとなりますが、上司に相談しても『結局、私に何をして欲しいの?』という返答をされることはないですか?
このような回答は私だけではなく、他の同僚や後輩も経験したとよく聞きます。勇気を出して相談しても冷たくあしらわれてしまうのは一体なぜなのでしょうか。
当パートでは、相談をするにあたって『必要な準備』を解説していきます。判断基準と準備さえしっかりできていれば、あなたは明日から相談におびえることはなくなるでしょう。
困っていることを明確に
何かを相談しようとするとき、皆様はどんなことに困っているかをよく考えていますか?
私は過去に相談内容が漠然としすぎて、上司に注意を受けた経験が星の数ほどありました。皆さんも以下のような経験をしたことがないか目を通してみて下さい。
【悪い相談例】

Aさん、お忙しいところ失礼します。〇〇の件で教えて頂きたいことがあるのですがよろしいですか?

いいけど、何がわからないの?

どうやって〇〇を完了させればいいかわからないのです。

…
具体的にはどこがわからないの?

それはですね、〇×△□….

話長いから、要点をまとめて質問してくれるかな、それじゃ。
いかがでしょう?
『要点まとめて』、『要点は何?』は上司の鉄板回答なのではと筆者は考えております。上記会話例で、私はどのような質問をすれば上司は答えてくれたと思いますか?

モチさんの本当に求めている答えだけを質問すればよかったのですかね?

まさにその通りです。仕事においての相談は抽象的なものではなく、限りなく具体的にしなければいけないのです!
何か相談するときは、とにかく困っている内容をより『細かく具体的』にすることです。最大の具体的相談は『Yes or No』の2択の質問です。
先ほどの私とA上司のやり取りであれば、下記例が良い相談となります。
【良い相談例】

Aさん、お忙しいところ失礼します。〇〇の件で教えて頂きたいことがあるのですがよろしいですか?

いいけど、何がわからないの?

〇〇を完了にするには、□ボタンか△ボタンどちらを押せばいいのでしょうか?

□ボタンを押した後にBボタンを押せばいいよ。

ありがとうございます!
先ほどの悪い例と比較して、相談することがシンプルになっていることにお気づきでしょうか?
上記のやり取りで大事だったのは、『□か△ボタンをどちらかを押すのか』であって、完了操作をするための状況報告はどうでもよいということです。

相談ってこんなシンプルでいいんですね。

もちろん内容にもよりますが、相談業務はできるだけシンプルに質問してください。
あなたも上司も仕事に追われていて暇ではありません。お互い時間を有効に使えるように『あなたが何に困っているのか』を明確にして、聞く側の負担をできるだけ減らすようにして下さい。
上記やり取りは□か△の極端な例ではありますが、業務の相談は『OK』か『NG』の指示をもらうことがベストだと思っています。

しかし、私は具体的な相談内容を整理できる自信がありません。

そんな方は、まずは文章化して情報を整理しましょう。
情報は書いて整理
相談するときは質問する内容を明確にすることが大切ですが、自分が困っていることを具体的に整理できないという人も多いかと思います。
私も得意な方ではないのですが、そんな時は『書いて』質問事項をまとめていました。

書くことで客観的に何が問題なのか理解できるのでとてもおすすめです!
また、問題提起を文章化できるようになると、相談しようと考えていたことが不要と判断できることもあります。例えば、この情報はマニュアルに書いてあったなと、書くことで気づくことも出てきます。
どれが必要でどれが不要かの情報を整理するためにも、『書く』ことは非常におすすめな方法なので、是非試してみて下さい。

箇条書きにして書くと、より不明点がわかりやすくなります。
問題点が明確になれば、あとは相談するのみとなります。しかし、相談は報告業務と同じように『端的』に伝えなければ注意を受けてしまいます。
業務上の伝え方について知りたい方は、別記事の業務報告で伝える4つのポイントとは?を参考にして上司や同僚に声をかけてみて下さい。

なるほど~
これで上手く相談ができる気がしてきました!
まとめ
今回の仕事の悩みテーマ、『相談ができない』はいかがだったでしょうか?
当記事を読んだことで、今まで躊躇していた相談業務に抵抗がなくなったのであれば、筆者は大変うれしく思います。

最後におさらいをしましょう!
業務に不明な点があれば、相談をするという行為は決して悪いことではありませんが、相談をする前に以下2つを怠っていると、逆に注意を受けてしまうケースがあります。
- 判断基準の定義
- 準備

判断基準には、3つの項目がありましたよね。
- ググってわかる情報
- 自分が管理している情報
- 既に教えてもらった情報
準備においては、『自分が何に困っているのか』を明確化させることが非常に大切になります。
『判断基準』と『準備』さえしっかりできていれば、相談することはほぼ成功します。それでも相談にのってくれない人は、人として何か問題があるのではないかと思います。
人に何か聞きたいときは、できるだけ話をまとめること肝心です。友達ならまだしも、職場は1分1秒の時間が惜しいところもあります。
相談はあなた主体ではありますが、『相手のことも考えて質問する』ことを心掛けてみましょう。そうすれば相談相手にあなたの誠意が伝わり、親身になって応えてくれると筆者は信じております。

また、当記事以外にも仕事の悩みがある方は、朗報です!
当ブログにはじめて立ち寄られた方、仕事に悩みを抱えている方はいませんか?
当ブログは、本記事以外にも仕事の悩みの解決方法を紹介しております。効率的に仕事ができるコツを各記事で確認できるので、興味がある方は是非『仕事の悩み』をクリックして目を通してみて下さい。
きっと何かしらの問題解決、または解決のヒントになると思います。
ここまでお読み頂き、誠にありがとうございました。また次回の記事で皆様にお会いできることを楽しみにしております!


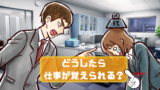



コメント